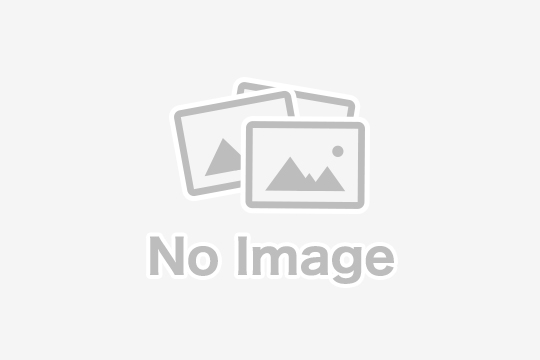西部謙司氏は日本のサッカー解説者であり、その卓越した知識と洞察力で多くのファンやサッカー愛好者に感銘を与えています。彼の著作物はサッカーの戦術や歴史に深く踏み込み、その解説は理解しやすくかつ情熱的。また、解説の中で独自の視点からサッカーの魅力を伝えており、彼の論評はサッカー界において一石を投じています。
西部謙司氏は子どもから大人まで、幅広い層に向けてサッカーの楽しみ方や理解を提供しています。彼の講演や執筆活動は、サッカー愛好者にとって貴重な情報源となっています。その深い洞察と情熱的な伝え方により、サッカーに興味を持つ人々にとって西部謙司氏は頼りにされている存在です。
サッカーの戦術を考える西部謙司氏の著作物
「子どもがサッカーをやっていて大人は何を楽しめばよいのか?」と言うときに、この本を片手に見ると、子どもが歴史の系譜に刻まれるのではと勘違いできるかもしれません。
【参考】西部謙司氏の著書はこちら
戦術クロニクル
▶戦術クロニクルⅠ
読めばサッカー観戦がもっと面白くなる!
西部謙司氏の『サッカー戦術クロニクルⅠ』は、サッカーの歴史を「戦術」という視点から紐解き、現代サッカーの戦術がどのように進化してきたのかを教えてくれる一冊です。単なるフォーメーションの解説ではなく、「なぜその戦術が生まれたのか?」「どんな影響を与えたのか?」という背景まで深く掘り下げているので、試合を見る目が変わります。トータルフットボールを軸に、過去の名将や名チームの戦術を分析することで、現代サッカーの戦術のルーツが見えてくるでしょう。試合観戦がさらに深く、そして楽しくなること間違いなし!サッカー好きなら必読の一冊です。
クロニクルとは「年代記、編年史」の意味であり、戦術を覚えたい人向けの本ではなくて、サッカーの歴史だと思った方が良い内容。
▶サッカーの戦術クロニクルⅡ
サッカー観戦がさらにディープになる!西部謙司氏の『サッカー戦術クロニクルⅡ』は、前作に続き、ワールドサッカーの歴史を戦術という視点から徹底解説。単なる過去の戦術の紹介にとどまらず、現代サッカーに繋がる重要な要素を浮き彫りにしていきます。前作を読んだ方はもちろん、本作から読み始める方でも十分に楽しめる内容です。試合で繰り広げられる監督の意図や選手の動きがより深く理解できるようになり、観戦が格段に面白くなります。サッカーの奥深さを知りたい、もっと深く試合を楽しみたい、というサッカー観戦好きに自信を持ってオススメします。
サッカー4-4-2戦術クロニクル 守備陣形の復興と進化
未だ読んでいませんが、安くなったら古本で読んでみたいです。
上記読んだ本では、この本の内容を選手がゲームで活かすにはどうしても距離感があります。
そこはピッチの内、外どこから見ているかによるのでなんとも言えませんが、ポジションでの動きや組織、個人、何を考えて動いているのかに視点がいくようになるはず…
※ビリーはこういった本を読んで目が行くようになったわけではない。