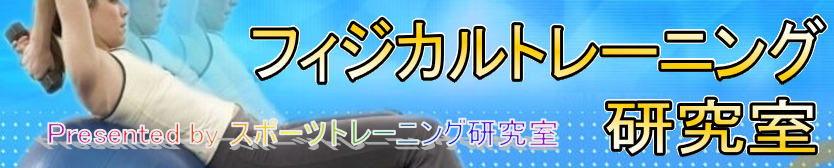競技内における、部分的な動作を分析してみましょう。野球では「走る、投げる、打つ」など様々な動作がありますが、一部を特化して考えてみます。
競技におけるスピードを分析をする
それでは実際に競技におけるスピードを、例として短距離走で分析してみましょう。
単純競技におけるスピードを分析する
①スピードの合図に対する反応スピード
②トップスピードまでの加速(ダッシュ)スピード
③トップスピード
(④トップスピードを維持する維持能力(スピードの持久性))
※④は筋持久力であるために括弧。
この様に単純競技では他の要素が非常に少ないために、遺伝の割合が必然と大きくなります。
各競技のスピードを分析する
 まずは各競技におけるスピードを上記の様に分析する必要があります。
まずは各競技におけるスピードを上記の様に分析する必要があります。
サッカーやバスケであれば、左右に動くスピード、ターンするスピード・・・と様々あり、実際には連動して行われます。
その分析からフィジカルトレーニングのメニューを作成しましょう。
スピードと筋トレの関係
またスピードは最大筋力に依存するため、筋トレが必要になります。
例えば写真のようなスタートをする時体を押し出す力は筋力であり、筋トレで最大筋力を上げるとその落ちだす力が増えます。
よく筋トレをすると運動能力が落ちると主張されますが、これは筋力が増すことで体と感覚がずれ(コーディネーションの差)が生まれるためです
このコーディネーションの差を埋めるためのトレーニングも必要になるのですが、そのトレーニングが普及されていません。
そのため、「筋トレ→フィジカルトレーニング→競技」この様な流れが正しい競技トレーニングと言えます。
投球動作であれば
例えば投球などの複雑な動きをする場合も、どのような順序でどのようなスピードが必要なのか明確に分析しましょう。
動画の文字と内容が異なりますが、あしからず。
投球動作のスピードを段階的に分析する
この分析は人によって異なります。
①まず振りかぶる時に脱力します。
②次に足を上げ、プレートを踏みながら体を前に押し出します。
③前足を地面につき、下半身を固定させます。
④腰を回転させながら上半身を連動させます。
⑤胸・肩と力を伝えます。
(以下関係ないので割愛…)
前半 体を加速させる
自身の分析に沿ってトレーニングメニューを考えることになります。
- 瞬発力を生む前には脱力が重要と言う話があります。
力を入れすぎると体は硬直してしまい動けなくなるため、不要な部位は力を入れずに安定させることがスピードにつながります。
投球動作でのワインドアップポジションは脱力のためと考えています。 - 投球動作で最初に必要な力はこの押し出す動作。
瞬発力と考えると急に力を加えることになるので、バランスを取りながら安定させる必要が有るため、投球の押し出す動作には最大筋量が生むスピードが適切だと思います。
→最大筋量を増やすトレーニングは筋力トレーニングにほかなりません。 - 足をつく動作も急激に行うと、全身を支えるのではなく、投球方向とは逆向きのスピード(抵抗)になります。
あくまでも支えて次の動作へのつなぎという意識が重要になります。
→バランス能力はインナーマッスルのトレーニングが適切ですが、ここで必要なバランス能力はコーディネーション能力でもあるので、体全体を動かすランニングやダンスなどが適切です。
ここまではあくまで体全体のスピードを生むための話。
後半 体のスピードをボールへ伝える
後半は体全体で生み出したスピードをボールへ集約して伝えるための話。
- ③の足が付いた瞬間から骨盤を回転させ始めますが、この動作によりボールのスピードが上半身へと伝えられてボールのスピードが増すことになります。
そのため、体を回転させるスピードも重要になります。
→左右と対になる筋肉のトレーニングで使える筋肉を増やし、
インナーマッスルのトレーニングにより、バランスを取る(支える)筋肉を増やすことが必要になります。
インナーマッスルに対しては諸説あります。
【補足】>インナーマッスル - ⑤骨盤から腹筋へ伝える際にも腹筋の力を加えることで加速します。
さらに胸を張り肩へ正確に力を伝えることで加速させ、
力を腕へと伝えます。
競技動作を分析し、全てを分けてトレーニングする
このように実際は複合的な動きの中にあるため、動作を細かく分析し、トレーニング内容もそれぞれ対応させる必要があります。
本来必要になる投げ込み練習は、分析により分けられたトレーニングに連動性をもたせるトレーニングの一つでもあります。
そのため全力で投げ込む必要はなく、軽い投球動作やボールを持たない軽いシャドーピッチングでも良いのです。
この様に少し細かくすることで肩の疲労を軽減させることもできます。
ボールリリース後のフィールディングも分けて考えましょう。
バランスを崩した状態から機敏さ、俊敏さなどを求めるトレーニングも一見複雑に思えますが、
半円型のバランスボールで片足立ちなどでトレーニングすることができます。